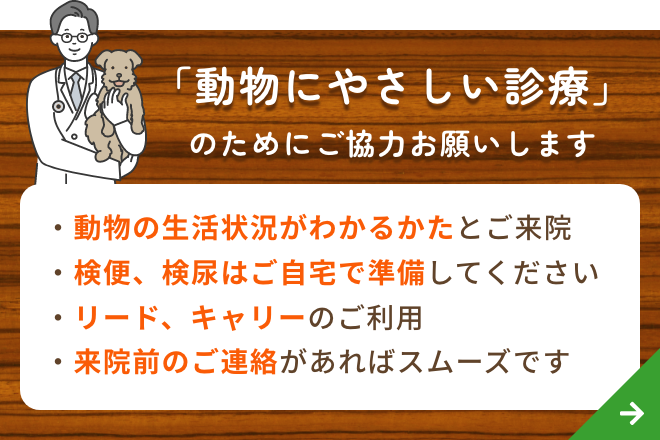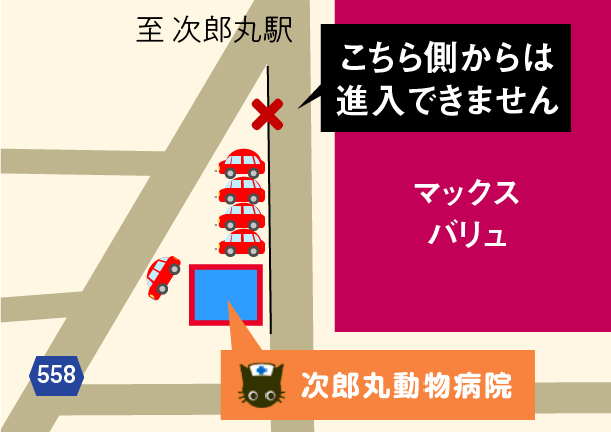「動物の皮膚病をどうやって治療するの?」各論編10|心因性の皮膚病|獣医師が解説
皮膚科 症例紹介「動物の皮膚病をどうやって治療するの?」各論編10|心因性の皮膚病|獣医師が解説
福岡市早良区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市中央区、糸島市のみなさん、こんにちは。
福岡市早良区の次郎丸動物病院の獣医師の矢野です。
「獣医師は動物の皮膚病をどうやって治療するの?」今回は、当院で治療を得意としている皮膚病について、動物を飼育する皆さんが素朴に抱くこの疑問について解説しようと思います。「概要編」「検査編」「診断編」「各論」という形でシリーズとして述べさせていただきます。今回は「各論編10」最終回です。(ブログ記事を最初からご覧になりたい方はここをクリック)
【25.心因性の皮膚病】
ペットの皮膚病には、ストレスや不安などの心理的な要因が深く関与している場合があります。このような皮膚病は「心因性皮膚病」と呼ばれ、行動問題と皮膚症状が結びついています。今回は、心因性の皮膚病の原因、症状、そしてその対策について解説します。
心因性皮膚病の主な原因
ペットは環境の変化や生活習慣の乱れ、飼い主との関係性など、さまざまな要因でストレスを感じ、それが身体的な症状として現れることがあります。特に以下のような要因が心因性皮膚病に関わることが多いです。
• 生活環境の変化: 引っ越しや新しい家族(他のペットや赤ちゃん)の加入、家族の不在などの変化により、不安や緊張を引き起こすことがあります。
• 孤独感: 長時間の留守番や飼い主とのコミュニケーション不足によって、孤独感がストレスとなり、皮膚に異常をきたす場合があります。
• 運動不足や刺激不足: 十分な運動や遊びが不足していると、エネルギーが余り、それがストレスとなって皮膚を過度に舐めたり、掻いたりする行動に繋がります。
心因性皮膚病の症状
心因性の皮膚病では、次のような症状が見られることがあります。
• 過剰な舐めや掻き行動: 特に足や尻尾などをしつこく舐める行動は、ストレスのサインです。この行動が続くと、毛が抜けたり、皮膚が赤く腫れて炎症を起こしたりすることがあります。
• 脱毛: ストレスや不安によって毛が抜ける「ストレス性脱毛」が見られることがあります。特定の部位で対称的に脱毛が起こる場合もあり、病気としての皮膚病と見分けがつきにくいことがあります。
• 皮膚の赤みや炎症: 過剰なグルーミングや掻きむしりによって皮膚に傷がつき、そこから炎症が広がることがあります。これは、二次的な皮膚感染症を引き起こす可能性もあります。
診断
心因性皮膚病の診断には、まず身体的な原因(寄生虫、感染症、アレルギーなど)を除外する必要があります。これには皮膚検査や血液検査が含まれます。身体的な原因が特定できない場合、心因性である可能性が高まります。
治療
治療は以下のアプローチが効果的です。
• ストレス源の特定と除去: 環境の変化や日常生活の中でペットが感じているストレスの要因を見つけ、それを取り除いたり、改善したりすることが最優先です。
• 生活環境の改善: ペットにとって快適な生活環境を整えることが重要です。運動や遊びを増やし、心身のリラックスを促す時間を確保しましょう。飼い主とのコミュニケーションを増やすことで、ペットの不安を軽減できます。
• 行動療法: 必要に応じて、行動専門の獣医師と連携し、ペットのストレス反応を緩和するための行動療法を行うことが効果的です。
• 薬物療法: ひどいストレスや不安を抱えているペットには、抗不安薬やサプリメントを使用することもあります。ただし、薬物療法は短期的な対策であり、環境改善と併用することが推奨されます。
まとめ
心因性皮膚病は、ペットが示すストレスや不安のサインの一つです。早めに症状を認識し、適切な対策を講じることで、皮膚症状を改善し、ペットの心身の健康を保つことができます。皮膚に異常が見られた際には、まず獣医師に相談し、心因性の可能性も視野に入れた診断を受けることが大切です。
この子は左右対称性に腿の部分とお腹に赤みや湿疹を伴わない脱毛が見られます。飼い主さんは「ずっと舐めてる」ことを主訴に病院を訪れ、各種皮膚検査で寄生虫や酵母や真菌が否定的で、ステロイドの治療にも反応がないことから心因性の皮膚炎が疑われる事例です。皮膚表面を良く見ると、舐めすぎていることから発毛はあるが、毛が途中から切れているような脱毛を認めます。治療としては、姑息的な方法としてエリザベスカラーの着用や生活環境の整備などで対応しています。精神安定剤などの使用を検討することもありますが、体全体の異常につながる恐れがないときは、ある程度の治療で経過観察とすることもあります。